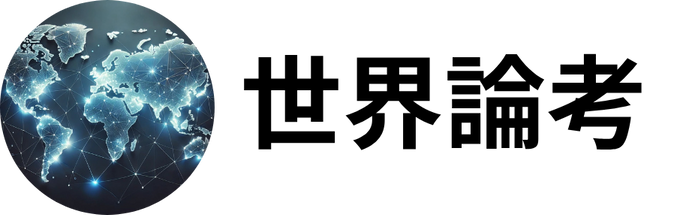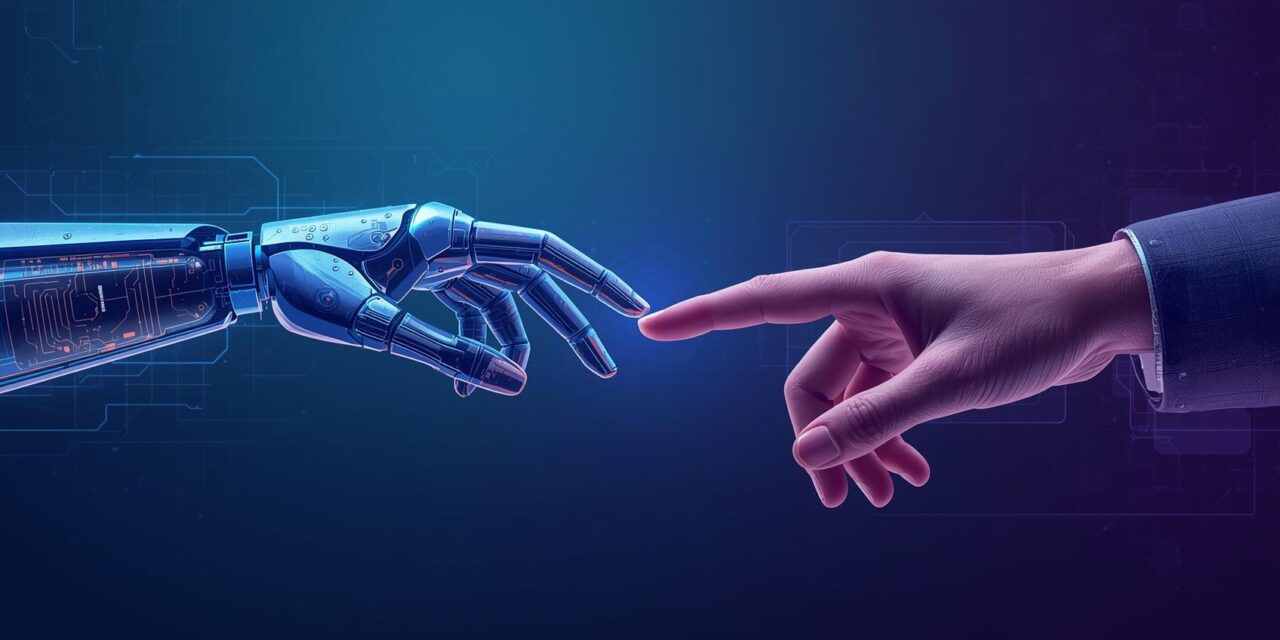AIが人間の代わりに商品を選び、購入手続きを済ませる──そんな未来像は魅力的に聞こえます。しかし、現実にはAIコマースはほとんど前進していません。技術的には可能でも、社会的には受け入れられない。なぜAIは「お金を動かす責任」を担えないのか。本稿では、決済エンジニアの視点から、AIコマースの限界と人間中心の設計思想を探ります。
背景・問題提起:AIコマースが抱える「既視感」
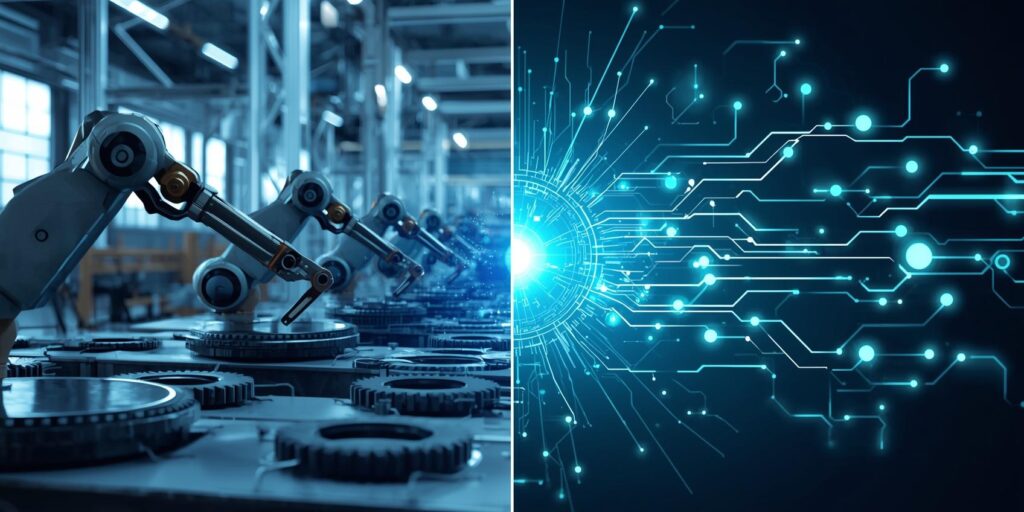
RPAが示した自動化の限界
AIコマースの議論は、かつてのRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)ブームを思い起こさせます。ボタン操作や入力作業を自動化できるRPAは、一時期「数百万人の仕事を奪う」と恐れられました。しかし、最終的にRPAは一部の業務改善にとどまり、大規模な失業も革命も起きなかった。
AIコマースも同様に、理論的には可能でも「人間の期待」を超えることは難しいのです。
「人間不在の購買」が社会的に受け入れられない理由
私たちは商品を「選ぶ」だけでなく、「信頼」して購入しています。支払いは単なる取引ではなく、心理的な安心感を含む行為です。AIがそのプロセスを代行すると、購入の責任や判断の正当性が曖昧になります。技術の問題ではなく、信頼と責任の問題なのです。
AIは本当に「購入者」になれるのか
AIがオンラインで商品を注文すること自体は可能です。しかし、それが「誰の意思」なのかが問題になります。AIが本人確認や承認を代行できない限り、取引の主体は常に人間である必要があります。この「本人性」をAIが担保できないことが、AIコマースの最大のボトルネックです。
メカニズム・理論:AIコマースが成立しない構造的理由

認証と承認のギャップ
オンライン取引には、ユーザーの認証(本人確認)と承認(支払いの許可)が不可欠です。AIがこれを代行するには、明確なルールと責任の所在が必要ですが、現在のAIにはその枠組みがありません。「AIが誤って注文した場合、誰が責任を取るのか?」という問いに答えられない限り、AIコマースは信用されません。
「真正性」という概念の曖昧さ
開発者たちは「AIがユーザーの意図を正確に再現できること」を“真正性”と呼びます。しかし、自然言語による指示は常に曖昧で、AIは解釈を誤る可能性を持っています。AIが“意図を推測して行動する”構造自体が、商取引のリスク要因となっているのです。
幻覚(Hallucination)の問題と「可逆性」
AIが誤って存在しない商品を購入した場合、誰が返金を処理するのか?記事では、AIがミスを犯すことを前提に「取引を簡単に取り消せる仕組み」が必要だと指摘します。つまり、AIコマースは「幻覚を起こす前提で設計されるべき」なのです。
応用・社会的影響・実例:責任を取るのは誰か

販売者(MoR:Merchant of Record)のジレンマ
AIが自動で購入する場合、そのAIが「販売者」として記録される必要があります。しかし、OpenAIなどの企業は「私たちは販売者ではない」と明確に線を引いています。つまり、AIが購入を行っても、誰もその取引の責任を負わないのです。
この構造は、カード決済が登場した当初の「誰がリスクを負うか」という議論を再現しています。
Julie Fergusonの実験──AIコマースの現実
Merchant Risk CouncilのCEOであるジュリー・ファーガソン氏は、Perplexity AIを使って実際にオンライン購入を試みました。結果、支払いも配送も問題なく完了したものの、体験としては従来のオンラインショッピングとほとんど変わらなかった。つまり、「AIによる購買体験」はすでに実現しているが、“それ以上でも以下でもない”のです。
Airbnbが築いた「人間中心の支払い」
Airbnbは「支払いをより人間的にする」ことで成功しました。見知らぬ人同士がお金をやり取りする取引を成立させたのは、テクノロジーではなく信頼の設計です。AIコマースには、この“信頼を設計する力”が欠けています。AIがどれほど賢くなっても、支払いの「人間らしさ」は置き換えられないのです。
今後の展望や議論:AIコマースが進むべき現実的方向

「自動購入」より「支援的AI」へ
AIが買い物を“代行”するよりも、“支援”する形の方が現実的です。たとえば、購入候補を提示したり、支出を最適化したりするAIアシスタントです。最終的な決定権を人間に残すことで、責任と信頼のバランスが保たれます。
社会が求めるのは「完全な自動化」ではない
消費者が求めるのは「効率」だけではなく、「納得感」です。AIがすべてを自動化するのではなく、人間が安心して選べる範囲を広げることこそ、真の意味での“AIコマース”の進化と言えるでしょう。
「人間中心のAI設計」がフィンテックの未来を決める
AIが購買を完全に担う未来は遠いかもしれません。しかし、AIが支払い体験を補助し、よりスムーズに、より安心して取引できる環境を作ることは可能です。そのためには、テクノロジーだけでなく、倫理・法・UXデザインを含めた「人間中心の設計」が不可欠です。
まとめ・考察
AIコマースは技術的には成立しても、社会的には成立していません。
それは、「誰が責任を取るのか」「AIの判断は人間の意図と一致しているのか」という根源的な問いが解決されていないからです。
AIが人間の代わりにボタンを押す未来よりも、人間がより賢く選択できる未来の方が、ずっと現実的で豊かです。
支払いは、数字や手続きではなく、信頼という人間的行為なのです。