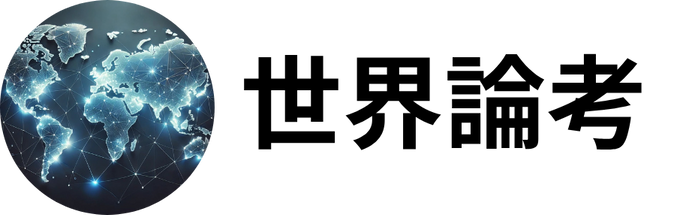「人生の幸福はU字を描く」と聞いたことがあるでしょう。若い頃に幸福度が高く、中年期に落ち込み、老年期に再び上がる──そんな「幸福曲線」は、数十年にわたって心理学や経済学で信じられてきました。
しかし最新の進化人類学研究は、この曲線が人類普遍の法則ではなく、「西洋的な生活様式」の反映にすぎないことを明らかにしつつあります。では、幸福の形とは本当に普遍なのか、それとも社会ごとに異なるものなのでしょうか。
背景・問題提起:幸福は「U字型」を描くという通説

長年、幸福学や経済学では「生涯幸福度はU字型を示す」と信じられてきました。若年期には健康や自由があり幸福度は高く、中年期には家庭や仕事の責任で一時的に低下。老年期に入ると再び上昇する──こうしたパターンは欧米の大規模調査でも繰り返し確認されてきました。
さらに興味深いことに、チンパンジーやオランウータンでも似た傾向が見られるとする研究まで発表され、「U字型幸福曲線」は生物的・普遍的現象とみなされてきたのです。
WEIRDバイアスという落とし穴
しかしこの通説には、研究対象の偏りという重大な問題がありました。多くの幸福研究は、WEIRD(Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic)社会──つまり「西洋の、教育を受け、工業化され、裕福で、民主的な」社会の参加者に偏っていたのです。
この限られたサンプルで得られた結果を、人類全体の普遍的な傾向として一般化することは妥当なのか。進化人類学者マイケル・ガーベンは、そこに疑問を投げかけました。
メカニズム・理論:小規模社会で見えた「別の幸福曲線」
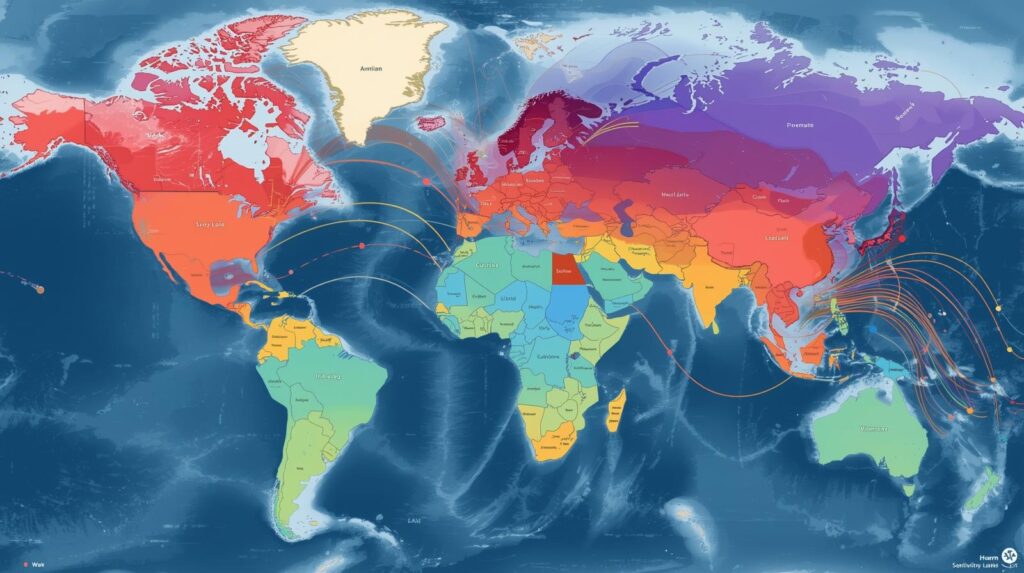
ガーベン氏はボリビアの小規模農耕・採集社会を観察し、高齢者の幸福度が加齢とともに低下する傾向を発見しました。肉体労働が中心の生活では、健康の衰えがそのまま生活困難につながるためです。
対照的に、欧米の高齢者は退職後に労働負担が減り、社会的保障にも守られるため、幸福度が回復する傾向を示します。つまり、U字型幸福曲線は、特定の社会構造に依存した現象なのです。
9,000人・20カ国のデータが示す「幸福の多様性」
Science Advances誌に掲載されたガーベンらの研究では、ラテンアメリカ、アジア、アフリカの20カ国以上で暮らす9,000人を対象に幸福度を調査。その結果、U字型を描く社会はほとんど見られませんでした。
多くの地域では幸福度が横ばい、あるいは年齢とともに低下。中には逆U字型──若年期が最も幸福という傾向も確認されました。幸福と年齢の関係は、文化・経済・環境要因によってまったく異なっていたのです。
年齢よりも「生き方」が幸福を左右する
特に注目すべきは、幸福度の変動のうち年齢で説明できるのはわずか5%未満だったという事実です。
作物の不作や病気など、日々の生活を脅かす出来事の方が、年齢よりはるかに幸福度に影響していました。幸福は時間の経過ではなく、生活条件と社会構造によって形づくられているのです。
応用・社会的影響・実例:先進国にも影響する「幸福の再定義」

この研究は、発展途上地域だけでなく、長寿化が進む先進国にも示唆を与えます。健康寿命と実際の寿命の乖離が広がる現代社会では、老年期に再び幸福が上昇する保証はありません。
社会のセーフティネットが脆弱化すれば、かつての「U字の上昇部分」は失われるかもしれません。
「社会的価値」を持つことの重要性
ガーベンらは、自給自足社会では「生産的で価値ある社会の一員であること」が幸福度を左右する最大の要因であることも発見しました。社会的貢献を果たせなくなると、信頼や支援が得られず、幸福が急速に低下します。
これは、現代の高齢社会にも通じる教訓です。仕事や家庭から離れた後も、地域や社会に価値を提供し続けることが幸福を保つ鍵なのです。
今後の展望や議論幸福の「形」は社会ごとに異なる

今回の研究が示すのは、「幸福に普遍的な曲線など存在しない」という現実です。
文化、経済、環境、社会構造──それぞれの要素が幸福の時間変化を形づくる。幸福の“形”は、社会の鏡にほかなりません。
「幸福学」の再構築へ
今後の幸福研究には、WEIRD以外の社会を積極的に含めるアプローチが不可欠です。幸福を単なる個人の心理状態ではなく、社会的・生態的システムの一部として理解する。
それこそが、真にグローバルで人間的な「幸福学」への第一歩と言えるでしょう。
まとめ・考察
幸福のU字曲線は、人類共通の法則ではなく、西洋社会の生活条件を反映した一つの「文化的パターン」にすぎません。
ガーベンらの研究が示したように、幸福の形は社会構造・健康・生業・支援ネットワークなどによって大きく異なります。
人生の幸福とは、年齢で決まるものではなく、「どのように他者と関わり、社会の中で価値を生み出すか」によって決まる──。
私たち一人ひとりが、自分の「幸福の形」を描き直す時代が始まっています。